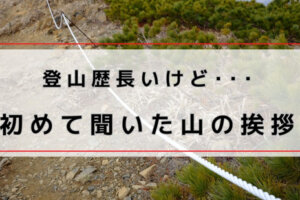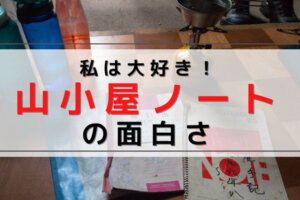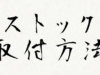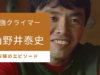こんにちは、寝袋!です。
あまり経験したくはないものですが、私は山でヒグマに遭遇したことがあります。
しかも、もう3回(2020年4月現在)も。
初めて遭遇した時は、心臓がバクバク鳴りました。
「予習していたことが頭の中から全部吹っ飛んで」何もできませんでした。
ヒグマに会ったらどんな気持ちなのか?
実際には何が出来るのか?
目次
1回目のヒグマ遭遇「幌尻岳にて」
私が初めてヒグマに遭遇したのは、日高山脈の幌尻岳に登ったときのことです。
秋晴れの天気が良い日で、気分よく歩いていました。
季節柄、他に登山者はいなくて、私一人しかいませんでした。
出た!
ふと気がつくと、前方15mほどのところに、何やら黒いものが・・・。
「うわっ出た!」
体が硬直して、動けませんでした。
ヒグマはやや小型で、若い個体に見えました。
ダケカンバの木の下に立って、両手を木の幹にあて、上を観ています。
こちらには、まったく気づいていない様子でした。
木の実?
こちらは硬直して動けないなか、ヒグマは木の上を観察していたかと思うと、スルスルと登り始めました。
「ヒグマって、木登り速ーい」
と、妙に感心しました。
ヒグマが木の上へ姿を隠したことで、金縛りが解けたように私も動けるようになりました。
まずは、クマ撃退スプレーを、腰のホルスターから取り出しました。
次に、ウエストポーチからカメラを取り出して、適当に撮影しました。(←ダメ)
「さて、これからどうすればいいんだろう?」
鈴を鳴らしまくる

私としてはヒグマが登っている木の下を通過したいので、なんとかしなければいけません。
避難小屋に1泊して、登山2日目なので、あきらめたくなかったのです。
「とりあえずヒグマに気づいてもらおう」
と、熊鈴を手にとって、派手に鳴らしてみました。
同時に、
「おーい、クマー」
と、大声で叫びました。
すると、ヒグマは一瞬動きを止め、こちらを見ました。
次に、ガサガサっと大きな音をたてて、ヒグマが木を降りて、そのまま登山道横の斜面を、下っていきました。
またもや硬直して動けなかった私。
ヒグマがちゃんと去ったのかわからなかったので、しばらくじっとしていました。
斜面の下へ逃げていったので、こちらからは見えなかったのです。
下をのぞくために、近寄る勇気もありません。
5分ほど待って(定かではないですが)、恐る恐るまた登山を続けました。
それからは、木の上ばかり見て、ビクビクと歩いた記憶があります。
1回目の遭遇まとめ
- 熊鈴は効果ありませんでした。
- ヒグマは、木の実に夢中でした。
- ヒグマは木登り得意です。
- ヒグマは、人に気付けば逃げていくことがわかりました。
2回目のヒグマ遭遇「芦別岳にて」

ヒグマとの2回目の遭遇は、富良野の近くにある芦別岳を登ったときでした。
初夏の芦別岳は、残雪がまだ多い時期ですので、登山者は私を含めて10名ほどでした。
無事に山頂まで登り、下山しているときのことでした。
樹林帯の登山道
かなり標高が低くなり、視界が効かない樹林帯の中の登山道になりました。
突然、20mほど先の登山道を、大きな黒いものが左から右へ横切っていきました。
ドドドッとすごい音がしました。
足を止める私。
「え? 今のはなんだ?」
北海道の山では、エゾシカが登山道に出てくることは日常茶飯事です。
それは、エゾシカではありませんでした。
「おいおい、またヒグマかー?」
1回目より落ち着いていた
この時、私は熊鈴はつけていましたが、クマ撃退スプレーは持っていませんでした。
幌尻岳で、
ヒグマは逃げていくもの
ということを経験したので、それ以来、クマ撃退スプレーは持たないことにしていました。
このときも、
「襲ってくるつもりなら、もう襲っている」
と、案外落ち着いていられたと思います。
ただし、心拍はバクバクで、耳から心拍の音が聞こえるくらいでした。
ヒグマが消えていった樹林帯の中に目を凝らしますが、まったく姿は見えません。
身を潜めているのか、逃げ去ったのか?
ゆっくりと前進しましたが、気配がわからないので、そのまま早足で下山しました。
下山すると、先に下山した人がいたので話をしました。
私のたった10分ほど前を、歩いていたようでした。
ヒグマは、すぎに逃げ去るのではなく、見えないところに身を潜めることが多いようです。
じっと、危険(人)が去るのを待つのです。
ところが、人間がいつまでもそこに立ち止まっていると、業を煮やしたヒグマは、攻撃に出ることもあるようです。
山菜採りがやられるのは、こういう理由もあるのです。
ヒグマが身を潜めて待っているのに、いつまでもそこに留まりますからね。
2回目の遭遇まとめ
- 熊鈴のおかげか、今回はヒグマが先に気づいた(?)ようです。
- ヒグマの足音はデカイです。
- おそらく10分ほど前に2名の登山者がいたのに、私だけが遭遇しました。
- やはりヒグマは逃げていくものです。
3回目のヒグマ遭遇「大雪山系にて」

3回目のヒグマとの遭遇は、大雪山系を縦走しているときでした。
過去2回とちがって、今回は視界がひらけている大雪山での遭遇でした。
視界良好
黒岳から白雲岳へ向かう途中、残雪の上を、ヒグマが動いていました。
距離がかなり(数百m?)あったので、白い雪面の上を、黒い点が動いているように見えました。
けっこうな斜面を、登っては滑り落ち、登っては滑り落ち、繰り返していました。
テレビ映像で観たことがありますが、どうやら雪面で遊んでいるようでした。
距離があるせいか、こちらには気づいていません。
仮にあちらに熊鈴がついていたとして、人間の耳ではまったく聞こえない距離でした。
近くにいた登山者と、
「遠くで見る分には、かわいいもんだ」
「遊んでる様子は、犬と変わりませんね」
と話しました。
そこから登山ルート(雪面)を進んでいくと、少しずつヒグマとの距離は縮まっていきます。
視界が効くので、安心して歩いていきました。
もし万が一向かってきたら、逃げても追いつかれてしまいますが・・・。
こういう遭遇なら大歓迎
それからも、ヒグマは気づいているのかいないのか、遊びをやめようとしませんでした。
地球をかすめるハレー彗星のように、登山ルートは近づいていきます。
お互いの距離は最短で200mほどまで近づき、そこからはまた、離れていきました。
やがて、振り返っても、見えなくなりました。
3回目の遭遇まとめ
- ヒグマも遊びます。
- ヒグマは雪面の登りも速いです。
- 遠い距離での遭遇は、大自然の贈り物です。
足跡と糞は無数に遭遇しています

日高山脈にて
ヒグマの姿を目で見た遭遇はこれだけですが、ヒグマの足跡はたくさん観ています。
また、ヒグマの糞も数え切れないほど観ています。
これは、北海道の登山者なら、かなり経験していることだと思います。
今では、
「いるんだなあ」
と感じますが、それほど恐怖は感じません。

オプタテシケ山、双子池にて
ヒグマとの遭遇まとめ
私自身を振り返ると、一番ヒグマが怖かったのは
- 1回目の遭遇をする前
- その遭遇の瞬間
でした。
その遭遇で、
「ヒグマは襲っては来ないものなんだ」
と身をもって経験できてから、それほど怖くなくなりました。
誰かに聞くのと、経験するのはやはり違いました。
私がこうやって経験を伝えても、やはり、なかなか信じられないかもしれません。
まあ、読んでいただいて、経験された時に、
「あ、あいつ嘘つきじゃなかったんだな」
と思ってもらえれば幸いです(笑)
もっとも大切なのは、ヒグマの生態を知り、遭遇しないように対策することです。
こちらの記事で詳しく書いています。
- ヒグマと会わないために
- ヒグマと会ったらどうするか
- ヒグマスプレーの使い方
などなど、ぜひ知っておいてください。
この本は本当にためになります。北海道先住民族アイヌの知恵。本当のクマ対策。